古来、中国より伝わってきた東洋医学は、今では日本でもよく発展し、特に日本人の鍼灸治療はどの国でも喜ばれるほど大きく発展・貢献してきました。
中国、日本、どちらにしても使うものは「漢字」。昔から伝わる何百ものツボには先人からの知恵が詰まっており、ツボに1つ1つ与えられた名前には深い意味が込められています。
精神と神
例えば、脳という概念がはっきりしていなかった時代には精神状態や意識状態を漢字一文字で「神(しん)」と捉えてきました。その影響で、気持ちを落ち着けるツボや精神疾患に使うツボには「神」という文字が使われていることが多いです。神門、神庭、神堂などなど。
蘇りとは
さてタイトルに話を戻しましょう。蘇りのツボと言いましたが、まず「蘇る」とは “いったん死んだ人が息を吹き返す。生き返る。転じて、いったん失せたものが、また力・命を取りもどす” といった意味です。もちろん、死んだ人が生き返ることは現実には難しいかもしれませんが、力を取り戻す、元気のなくなった状態から復活する、という意味では実感が得やすいかもしれません。そして、元気を取り戻す、というのは鍼灸や漢方を始め医学全般が行おうとしていることの本質であります。
薬師如来と魚
話は変わりますが、薬師如来をご存じでしょうか? 衆生の病苦を救い、どんな病気も治す薬を持っているという医薬の仏様です。奈良薬師寺の薬師三尊でも薬師如来が鎮座しております。こちらにある仏像、また、古くインドの仏石含め、足の裏に魚が刻まれています。
仏像の足にわざわざ刻まれている「魚」。「蘇る」という文字の中にも入っている「魚」。母なる海から生まれた私達にとっての祖先であり、生命の源である水の流れに逆らってまで産卵を行い種をつむいでいく「魚」。生物の中で、流れに逆らうのもまた魚のみなのです。現代では人間も流れに逆らおうとしていますが。
魚の力
こういったところから、古来より魚には神秘的な力、生命の根源たる力があると考えられていたのかもしれません。さらに、薬師如来の足の裏に刻まれている魚の絵、そこからさほど遠くない部分に「湧泉」というツボがあり、これは身体の中で水を象徴する腎という臓腑の井穴です。井穴とは、そこから力が出てくる、気が湧き出るツボの種類のことです。東洋医学における腎は「生殖機能」を司ります。さらにさらに、薬師如来の足の魚の位置を手になぞらえてみると、そこには「肺」のツボである「魚際(ぎょさい)」があり、肺は腎を力づけてくれる役割も担っているのです。
つながっていく文化と宗教と医学
多くのことがつながってきました。まとめてみましょう。
古来より母なる海に住んでいる「魚」に対し、先人達は強いエネルギーと神秘的な力を感じていたようです。それが仏教では人を癒す薬師如来の足に刻まれ、同じ位置に生殖機能を高める為に必須となる「腎(水)」の重要なツボがあり、さらには示し合わせたように手の同じ位置にはその力を強める魚の文字が入った「魚際」があるのです。

中国では古くから魚佩(ぎょはい)という2尾の魚をデザインした玉石を貴族のシンボルとしていたようです。薬師如来の足にも、同じく2尾の魚が刻まれていて、聖徳太子も魚佩を腰にぶら下げていました。今回の話とつなげれば、人の身体でいうこの2対の魚は手足のツボに宿っているのかもしれません。
人体に隠された魚の力
肺と腎は水分代謝を司り、呼吸もコントロールしています。様々な観点から見ても、古代人の知恵、魚という力強い生物と象徴に魅力を感じずにはいられません。こういったエネルギーや、それに合ったツボが、皆様の力を蘇らせてくれるかもしれません。
当院HPにてツボの取り方を見ることができますので、ご自宅で是非お灸やマッサージなどを試してみてください。
湧泉 ~動画で解説 – 妊活お灸のツボ事典より~

鍼灸師 西村 亮二
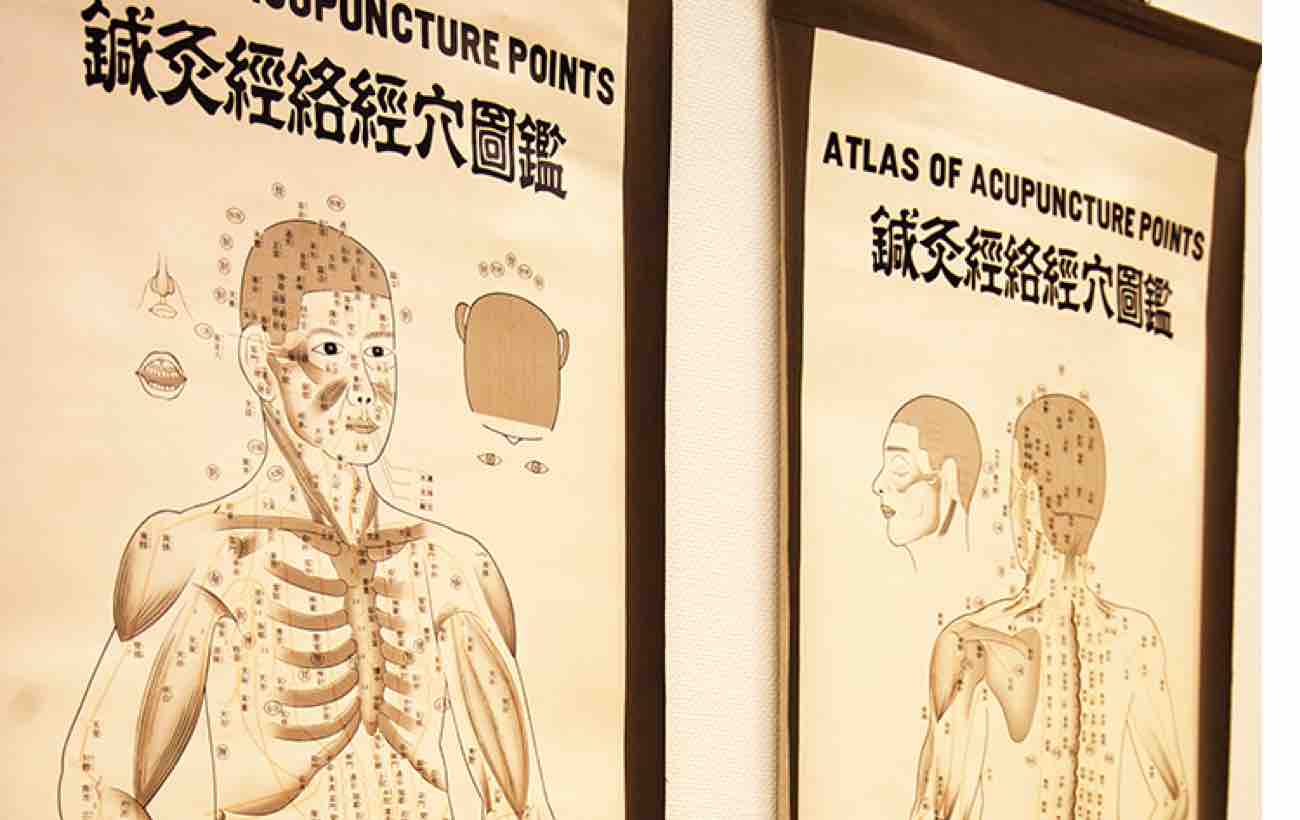

コメント